医師のご紹介
院長新川 恭浩(日本眼科学会認定 眼科専門医)

常勤長谷川 二三代(日本眼科学会認定 眼科専門医)
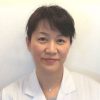
所属学会
日本眼科学会、日本弱視斜視学会、日本神経眼科学会経歴
平成4年 帝京大学医学部卒業
帝京大学医学部麻酔科学教室入局
平成6年 東京警察病院麻酔科派遣勤務・麻酔標榜医取得
平成7年 帝京大学医学部眼科学教室入局
平成9年 社会福祉法人 聖母会 聖母病院派遣勤務
平成12年 日本眼科学会眼科専門医取得
平成14年 聖母病院眼科医長
平成15年 医学博士取得
平成27年 社会福祉法人 聖母会 聖母病院退職
令和2年4月~ 新宿東口眼科医院 常勤医師就任
主な論文
眼科臨床医報 第91巻 第4号(1997年4月)学校における眼外傷の後遺症について
眼科臨床医報 第99巻 第5号(2005年5月)白内障術後に周期性が消失した周期性上下斜視の1例
帝京医学雑誌 第26巻 第3号(2003年5月)間歇性外斜視に対する遮蔽試験における眼球運動の定量的解析
- ※初めての方でもご予約可能です。
- 一般外来予約をする
- ドライアイ専門治療予約をする
- 小児眼科専門治療予約をする
- コンタクトレンズ診療予約をする






